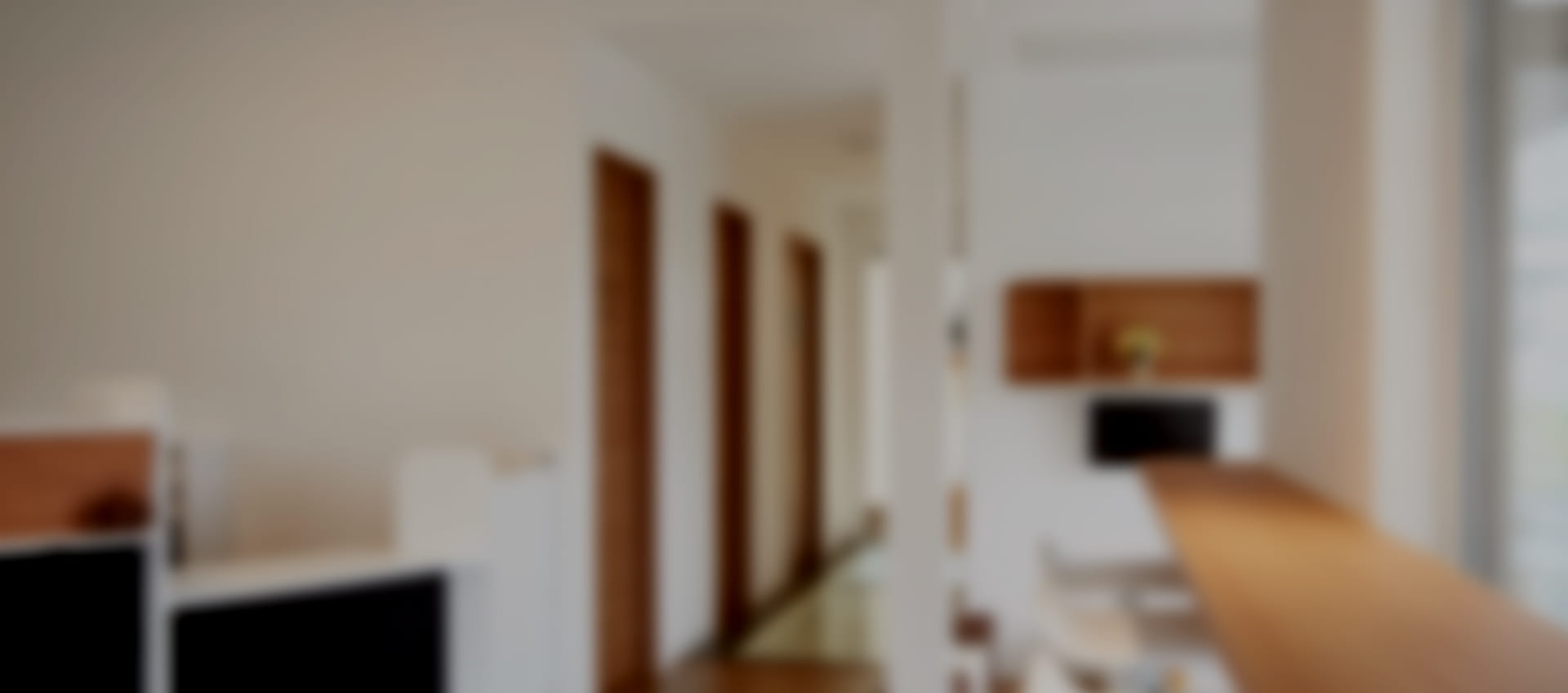JIADS エンドコース第3回目に行ってきました。
いつもお世話になっております。
高崎市箕郷町コープ敷地内で開業している、高崎ハルナモ歯科院長の深澤です。
https://takasaki-h-dental.com/doctor/
2025年4月26日、27日は医院をお休みにさせて頂き、ジアーズ エンドコースの第3回目に行ってきました。
ジアーズは正式名称をThe Japan Institute for Advanced for Dental Studiesと言います。
略してJIADSと表記します。
1984年に小野善弘先生と故中村公雄先生が、O-N Study Clubを前身とし、1988年にジアーズを発足されました。
ジアーズは、一言で表すとLongevity達成を目標としている、スタディークラブです。
Longevity(ロンジェビティー)とは、長期予後のことです。
ロンジェビティーを達成するためには、炎症と力のコントロールが必要です。
小野先生と中村先生はコンビを組まれ、小野先生が炎症のコントロールを、中村先生が力のコントロールをされていました。
炎症のコントロールとは、歯周病などの炎症疾患を治療することです。
力のコントロールとは、噛み合わせなどで生じる力を、生体に為害作用を及ぼさないように調整することです。
御二人の治療は、30年以上の長期予後を達成されています。
そのコンセプトを学べるのが、ジアーズです。
今回参加したコースはエンドで、炎症と力のコントロールでいうと、炎症にあたります。
エンドは、エンドドンティクス(Endodontics)を略した言い方です。
日本語だと、歯内療法とか根管治療といいます。
歯の中には、歯髄という神経と血管の複合体があります。
歯髄がある場所を歯髄腔といい、歯髄を取ることを抜髄と言います。
抜髄後に、根管充填材という材料をいれ無菌化を図ります。
根管充填後、複合的な要因で、歯根の先に膿の袋ができることがあります。
これを根尖性歯周組織炎といいます。
エンドは、抜髄後の根尖性歯周組織炎を未然に防ぐことと、根尖性歯周組織炎を治療することを目的とした治療体系です。
4月26日は、第1回(2/22.23)、第2回目(3/8.9)でもお世話になった先生方の講義を拝聴しました。
まず、京都市でご開業されている吉川宏一先生の講義から始まりました。
吉川先生は「ウィスキーが、お好きでしょ」で有名な田口俊さんと、高校の時にバンドを組んでいたそうです。
今でも音楽がお好きで、講義に入る前に必ず、先生のお好きな音楽を流されます。
講義テーマは、エンドサージェリーの診断と考え方でした。
根尖性歯周組織炎は多くの場合、根管内病巣が原因で、その結果として根尖病変ができます。
根管内の無菌化を達成すれば、根尖病変は縮小ないし消失していきます。
例外的に根尖口外の起炎物質が、原因になることがあります。
いくら根管内の無菌化を図っても、根管外に問題があるため治りません。
そのよう時、エンドサージェリーが適応になります。
エンドサージェリーは、歯根端切除(注1)と意図的再植(注2)という2つの術式があります。
本来なら歯根端切除を行うのですが、起炎物質の肉芽除去のみで対応された症例を見させて頂きました。
この症例を見させて頂くことで、歯根端切除の術式の意味を再認識できました。
次に埼玉県秩父市で秩父臨床デンタルクリニックをご開業されている栗原仁先生から、歯性上顎洞炎とエンドサージェリーについての講義がありました。
歯根端切除を行う際に、理想的にはどう行うべきか、理想的に行えない時はどう解決すべきか、という話をしていただきました。
歯根端切除の際には、逆根充(注3)というのを行うのですが、その際に使用する先生オリジナルの器材開発の裏話なども聞けて面白かったです。
その後、症例検討会を行いました。
他院の先生のスライドのクオリティーの高さに圧倒されました。
やはり症例写真を細かく撮ることで、手技の再確認になることを新ためて認識しました。
お昼休憩を挟んで、大阪で福地歯科医院を開業されている福地康生先生から、歯根端切除の実習の説明がありました。
縫合と視野を意識した切開線の設定の仕方、歯根端切除後の手技の手順など非常に勉強になりました。
その後、埼玉川口市で開業されている渥美克幸先生から破折ファイル除去の実習デモに移りました。
破折ファイルの位置による除去の難易度や可能性、実際の手技の進め方など新たに技術取得ができました。
27日は、東京都台東区で新御徒町やまぐち歯科医院を開業されている山口智子先生から、ガッターパーチャーの除去についての講義から始まりました。
ガッターパーチャーとは、根管充填材の代表的な材料です。
抜髄後、根尖性歯周組織炎になると、ガッターパーチャーの除去を行います。
ガッターパーチャーは、根管内で固まっており除去するのに苦労します。
ガッターパーチャーは一つの道具だけでは除去できず、複数のインスツルメントを使い分ける必要があります。
また根管の形態上、根管上部と根尖部の2つに分けて考える必要があります。
根管上部に何を使い、根尖部にはどんなインスツルメントを使うか具体的に教えて頂きました。
福地先生から、パーフォレーションリペアについての講義が次にありました。
パーフォレーションとは、治療中に穴があいてしまうことです。
この場合、しっかりとしたリペアを行わないと、感染してしまい抜歯をしなければならなくなります。
すぐに臨床で使えるシンプルで実践的な、診断と治療法がセットになったチャートを教えてもらいました。
栗原先生から、エンドと咬合の関係についての話がありました。
いくら良いエンド治療をしても、咬合関係がおかしいと長期的な予後にはつながらず、結果として局所治療になってしまうということを、症例を通して教えてもらいました。
岡山県で西阿知クォーツ歯科クリニックを開業されている、味村敏郎先生から接着のレクチャーがありました。
象牙質の部位により接着の程度に違いがあるため、材料を考える必要があると講義でおっしゃっていました。
超一流は、ここまでこだわるのかと感銘を受けました。
講義の最後に「人によって上達速度の差はあれど、続けるかぎり、必ず成功する。」という、まさにその時の自分にピッタリの言葉で締められていました。
この言葉を胸に、今後も精進していきます。
その後、渥美先生から歯髄温存療法の講義がありました。
歯髄温存療法とは、虫歯の進行のため本来なら抜髄が必要な歯に対して、特殊な薬剤を使用し神経の温存を図る治療方法です。
虫歯の進行により疼痛が出ている歯に用いることはできませんが、う蝕の進行が歯髄ギリギリの歯には非常に有効な治療方法です。
歯髄温存療法は自費診療で、確実に歯髄が保存できるわけではありませんが、色々な工夫をすることで成功率は上がります。
成功率を上げるための様々な工夫を教えて頂き、当院でも取り入れていきたいと思います。
昼食後、渥美先生から支台築造の講義と実習デモがありました。
歯内治療を行った歯は、被せ物をします。
支台築造とは被せ物の、土台を作ることです。
神経を抜いた歯は、未治療歯より脆くなるため、破折の可能性が高くなります。
しっかりとした支台築造を行うと、破折のリスクを下げられます。
今回教わった方法は、自費診療でしか行えない手技ですが、歯の保存を考えると非常に優れた方法でした。
最後に、吉川先生からジアーズ エンドコースの総括があり、終了となりました。
吉川先生から、「このコースは、先生方のエンド治療が楽しくなるのが目標です。」と話されていました。
受講期間の3ヶ月間を終わると、私も周りの先生方もエンド治療が楽しくなっていました。
エンド治療は、歯の保存には欠かせない技術です。
この3ヶ月間、朝練習を毎日したこともありますが、かなりエンドの治療技術が向上しました。
エンドを好きにさせてくれた「エンド4(カルテット)」(注4)の先生方には感謝しかありません。
高崎ハルナモ歯科では、一般歯科のみではなく、インプラント、矯正、ダイレクトボンディング、審美歯科などの高度な歯科治療を提供できるように、常に研鑽を行っております。
なにか、お困り事がございましたら、気楽にご連絡ください。
注1:歯根端切除とは、歯の根っ子の先端3ミリを切除することです。
注2:意図的再植とは、歯を抜いて先端3ミリを切除して、膿の袋を取ることです。
注3:逆根充とは、歯根端切除をした歯根の切除断面から、根管充填剤をいれることです。
注4:吉川先生、福地先生、栗原先生、渥美先生は2010年より、エンドコースの講師陣をされていて、エンド4と呼ぶそうです。