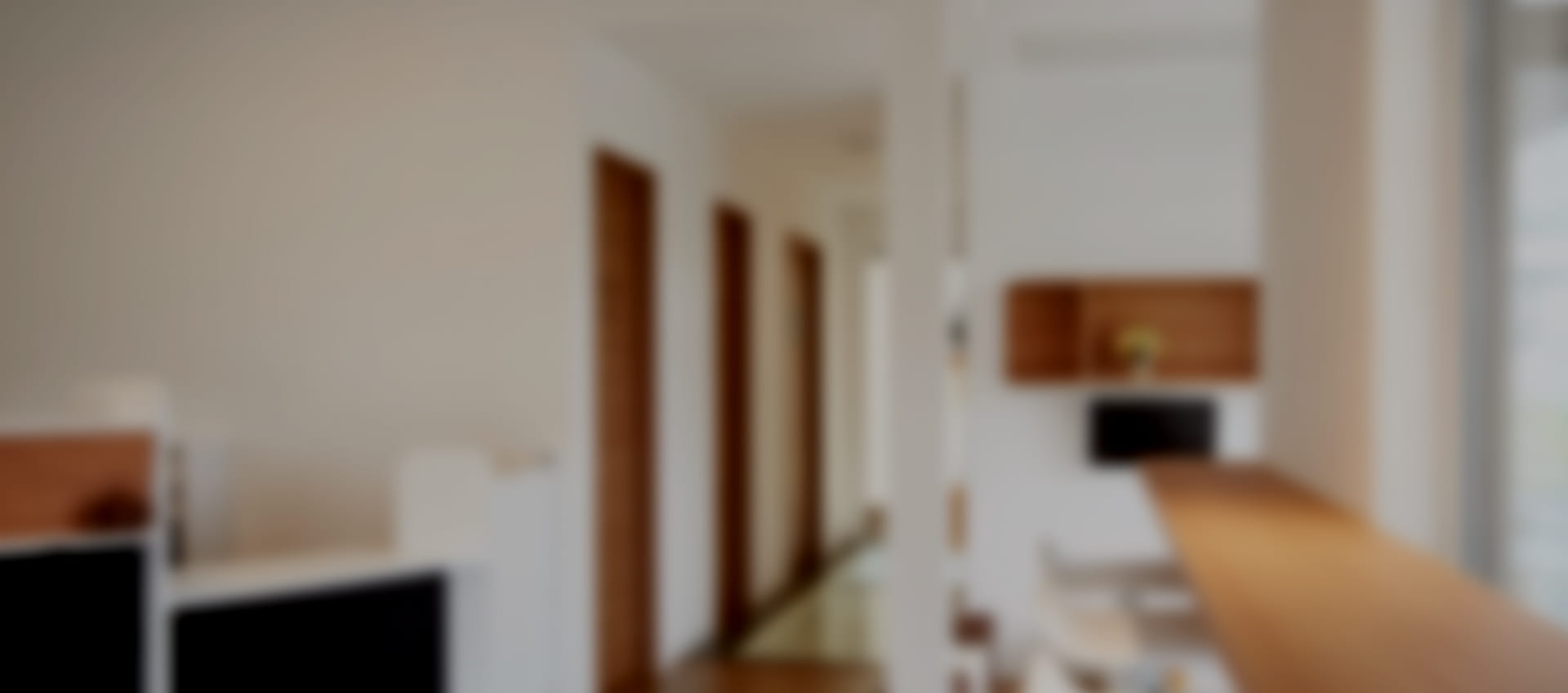JIADS ペリオコース第1回目に行ってきました。
いつもお世話になっております。
群馬県高崎市箕郷町コープ敷地内で開業しております、高崎ハルナモ歯科院長の深澤充です。
先日、3月15日(土)、16日(日)の2日間、JIADS(ジアーズ)のペリオコース第1回目に参加してまいりました。
JIADSは、1988年に発足された、日本の歯科界を牽引する著名なスタディークラブです。
その中でも「ペリオコース」と呼ばれる歯周病治療に特化したセミナーは、歯科医師であれば誰もがその名を知っているほどです。
第一線で活躍されている講師陣から直接指導を受けられる貴重な機会を得られました。
1日目のセミナーは、京都府でご開業されているタキノ歯科の滝野裕行先生による「ジアーズの紹介」からスタートしました。
滝野先生のお父様は某大学の内科教授として国内外でご活躍されていたという、まさに医療界の「サラブレッド」のような経歴をお持ちです。
しかし、その輝かしい背景とは裏腹に、ユーモラスで親しみやすいお人柄は、会場の緊張を一気に和らげてくださいました。
特に、ご本人曰く「夜のパトロールで超一流の野球選手の年俸を溶かした」という武勇伝には、会場も笑いに包まれ、先生の人間的な魅力が存分に伝わってきました。
滝野先生の講義は、単なる技術論に留まらず、歯科医師としての「あり方」や「哲学」に深く触れるものでした。
先生は、歯科医療における普遍的な成功の鍵として「3P+Passion」の考え方を提示されました。
これは、ジアーズ創設者の一人である小野善弘先生の師匠であるクレーマ先生が提唱された「3P」に、滝野先生ご自身の経験から「Passion(情熱)」を付け加えたものです。
「3P」とは、歯科医師の根源的な心構えを表しています。
一つ目はProfessional(専門性)。
歯科医療に携わる者として、その専門的知識や技術を学ぶことを常に怠ってはなりません。医学は日進月歩であり、新たな知見や治療法が次々と生まれています。
私たちは常に最新の情報を吸収し、自身の知識と技術をアップデートし続ける責任があります。
これは、患者様に最良の医療を提供するための大前提となります。
二つ目はPractical(実践)。
いくら専門的知識や技術を深く理解しても、それが臨床の現場で実践されなければ、絵に描いた餅に過ぎません。
学んだ知識や習得した技術を、目の前の患者様一人ひとりの症状や状態に合わせて適切に応用し、具体的な治療として落とし込んでこそ、真の医療となるのです。
頭でっかちになるのではなく、常に「どうすれば患者さんを救えるか」という実践的な視点を持つことが重要です。
そして三つ目はProfitable(有益性)。
たとえ知識や技術を習得し、それを臨床に応用したとしても、その行為が正しく評価され、患者様にとっても術者にとっても有益な結果とならなければなりません。
ここで言う「有益」とは、患者様の口腔内の健康改善、生活の質の向上、そして歯科医師自身の成長とやりがいといった、多岐にわたる価値を指します。
持続可能な医療を提供するためには、この「有益性」の追求も不可欠です。
滝野先生は、これら「3P」の根底に、歯科医師としてのPassion(情熱)がなければ、真に患者様の心に響く医療はできないと力説されていました。
どんなに素晴らしい知識や技術があっても、患者さんへの情熱がなければ、治療の成功は難しいというメッセージは、心に深く刻まれました。
また、ジアーズのコンセプトである「Conceptualization(概念化)」「Predictability(予知性)」「Longevity(永続性)」についても、実際の臨床例を交えながら教えていただきました。
これらの概念は、単に目の前の病気を治すだけでなく、その治療が将来にわたって患者さんの口腔健康を維持できるか、という長期的な視点を持つことの重要性を示しています。
特に印象的だったのは、「患者さんのモチベーションをいかに高めるか」という点に、滝野先生が力説されていたことです。
どんなに優れた歯科医師が高度な治療を行っても、患者さんご自身のセルフケアが不十分であれば、どんな治療もプラスになるどころかマイナスになってしまいます。
これは数多くの信頼性の高い論文で証明されており、今後この定説が覆ることは絶対にないと言い切れる事実です。
滝野先生が、夜の「パトロール」で培われたという軽快なトーク術で、患者さんの心をつかみ、治療への意欲を引き出す極意を教えてくださったことは、非常に勉強になりました。
歯科医療は、歯科医師と患者様が二人三脚で取り組むチーム医療なのだと再認識しました。
茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長の奈良嘉峰先生から、歯周基本治療の流れについて学びました。
雑誌などで拝見する写真以上に、実際にお会いすると大変なイケメンで、その端正な容姿にも釘付けになりました(笑)。
歯周病治療の流れは、日本歯周病学会から発行されている「歯周治療のガイドライン2022」にも明記されており、確立された治療プロセスが存在します。
私が学生だった頃から、基本的な流れに大きな変更はありません。
それにもかかわらず、なぜこれほど多くの歯周病患者さんがいらっしゃるのでしょうか。
奈良先生は、やはりここでも患者さんのモチベーション向上が欠かせないことを強調されていました。
私たち歯科医師は、歯周病を「歯肉の炎症が原因で、歯を支えている歯周組織と歯槽骨(歯を支える骨)が失われていく病気」と、その病態を理解しています。
しかし、多くの患者さんにとっての歯周病は、「歯茎が赤く腫れて、出血する」「歯がグラグラしてくる」といった、目に見える症状としての認識しかありません。
「骨の病気である」という認識は、ほとんど持たれていないのが実情です。
この歯科医療者側と患者さん側の「認識のズレ」を解消するためには、適切な「資料」を用いた説明が不可欠であると、奈良先生は強く訴えられました。
資料は、私たち医療者が治療効果を判定するために必要であるだけでなく、患者さんご自身に現在の状態を正確に伝え、治療の必要性を理解していただくために、極めて重要なツールとなります。
特に、患者さんに見せる際には、健康な歯周組織の「正常像」の資料と、歯周病が進行した患者さんご自身の「現在の状態」を示す資料を比較して説明することの重要性について、具体的な提示方法を交えながら詳しくお話しいただきました。
視覚に訴えることで、患者さんの理解度と治療への主体性が格段に向上することを改めて学びました。
次に、土岡歯科医院の土岡弘明先生から、歯周組織の基礎についての講義がありました。
大学時代に口腔組織学で学んだ内容ではありますが、改めて深く学び直してみると、その複雑性と奥深さに新たな気づきが多くありました。
講義では、特に「角化歯肉と付着歯肉の違い」や「生物学的幅径(Biological Width)」についての内容が中心でした。
これらの知識は、歯周病治療を行う上で極めて重要であり、ジアーズのペリオの考え方の基礎がここに凝縮されています。
セミナー後も、これらの内容を完全に自分のものにするため、何度も復習を行いました。
続けて土岡先生からは、歯周組織の検査とスケーリング・ルートプレーニングについての講義と実習がありました。
ジアーズでは、Cleansability and maintenability(清掃性と維持管理のしやすさ)の高い口腔内環境を作り、永続性を持った予知性の高い治療結果を目標としています。
この「予知性の高い治療結果」を追求するためには、徹底した現状把握が不可欠です。
そのため、ジアーズでは「ここまでやるの?」と驚くほど数多くの検査を行い、口腔内の状態を詳細に把握していきます。
特に歯周検査では、プロービングの深さや出血の有無だけでなく、様々な細かい注意点や測定のコツ、そしてそのデータをどのように解釈するかまで、詳細に教えていただきました。
SRPの実習では、歯石のつき方から、レントゲンでの検知度、そして術者の手で歯根表面の滑沢さを確実に得るための手技の「勘所」などを、微に入り細に入り教えてもらいました。
非常に情報量が多く、とても1回で全てを吸収できるものではありませんでしたが、現在まで何回も復習し、当院のスタッフとも協力しながら練習を重ねています。
より精密なSRPを提供できるよう、今後も技術向上に努めてまいります。
1日目の講義終了後には、ウェルカムパーティーが開催されました。
この会では、講師の先生方や全国から集まった受講生の先生方と、歯科医療に関する熱い議論を交わすことができました。
先生方との交流は、新たな視点や情報をもたらし、非常に刺激的な時間となりました。
2日目は朝の8時30分から、酒井歯科クリニックの酒井和人先生による、歯周治療に必要な資料採得についての講義から始まりました。
歯周病治療は、単に歯の清掃を行うだけでなく、歯を支えている歯槽骨の治療であるという認識が非常に重要です。
そして、その歯槽骨の状態は、歯肉や口腔内の粘膜に現れます。
そのため、治療開始前の口腔内の状態を正確に記録し、治療の経過を追跡するためには、口腔内写真とレントゲンが不可欠となります。
酒井先生は、特に写真撮影やレントゲン撮影の「規格化」の重要性を強調されました。
設定や撮影方法が毎回異なると、正確な比較ができなくなり、治療効果の評価が難しくなります。
そのため、写真撮影における適切な設定(ISO感度、絞り、シャッタースピードなど)や、使用する機材(一眼レフカメラ、リトラクター、ミラーなど)、さらにはレントゲン撮影時のポジショニングに至るまで、非常に細かく、そして実践的な内容を教えていただきました。
これにより、常にブレのない正確な資料を採取し、患者様への説明や治療計画の立案、そして治療後の評価に役立てられるようになります。
当院でも、この規格化を徹底し、より質の高い資料採得に努めてまいります。
その後、土岡先生から、スケーリングとSRPの限界についての講義がありました。
スケーリングとSRPのみでの歯石除去には限界があり、歯周病が進行したケースでは、より深い部分の歯石除去や病変組織の除去のために、歯周外科処置が必要になることを、最新の文献を参照しながら丁寧に教えていただきました。
「それなら、最初からスケーリングとSRPを行わずに、いきなり歯周外科をすればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
術前にスケーリングとSRPを行うことで、歯肉の炎症が消退し、歯周組織の状態が改善されます。
炎症が残っている状態では、麻酔が効きにくかったり、出血が多くなり術野が見えにくくなったりと、外科処置が非常に困難になります。
また、スケーリングとSRPによって歯周組織が大きく改善され、外科処置の必要がなくなるケースも少なくありません。
スケーリングとSRPは、外科処置を行うかどうかの判断や、外科処置を安全かつ確実に行うための「準備段階」として、欠かせない治療なのです。
さらに、SRP時に歯石を取り残しやすい解剖学的な特徴を持つ部位についても、詳細な解説をいただきました。
講義の最後は、関根歯科医院の関根聡先生から、歯周外科処置の基本テクニックについての詳細な講義がありました。
今回のセミナーで取り扱う主要な歯周外科の術式について、その分類、適応症、そして具体的な手技を教えていただきました。
具体的には、Open Flap Debridement(オープンフラップデブライドメント)、Modified Widman Flap(モディファイドワイズマンフラップ)、Apically Positioned Flap(アピカリーポジショニングフラップ)、Coronally Positioned Flap(コロナリーポジショニングフラップ)、Free Gingival Graft(フリージンジバルグラフト)、Connective Tissue Graft(コネクティブティッシュグラフト)、Regenerative Therapy(再生療法)といった術式です。
これらの術式について、それぞれの特徴や患者様の状態に応じた選択基準を学びました。
特に、Apically Positioned Flapを例にとり、歯周外科に必要な外科処置のテクニックを、非常に詳細なスライドを用いて説明していただきました。
切開線、剥離の範囲、縫合方法など、一つ一つのステップを丁寧に解説してくださり、イメージを具体的に掴むことができました。
理論的な講義の後は、いよいよ実習です。
今回は、歯周外科の中でも基本となるオープンフラップデブライドメントを、ステップ・バイ・ステップで解説してもらいながら、模型を使って行いました。
一つ一つの器具の持ち方、メスの角度、歯肉組織の操作方法、そして縫合の仕方まで、非常に細かく指導していただきました。
この実習は、次回以降のより複雑な歯周外科処置へと繋がる重要な基礎固めとなります。
模型上での手技の習得は、実際の患者様への治療に臨む上で不可欠な自信と正確性をもたらしてくれます。何度も繰り返し練習し、確かな技術を身につけることの重要性を痛感しました。
今回のJIADSペリオコースで、歯周病治療の奥深さ、そして患者さんのモチベーション向上の重要性を再認識し、より質の高い歯科医療を提供するための多くのヒントと技術を得ることができました。
高崎ハルナモ歯科では、今回の歯周病治療の研鑽だけでなく、一般歯科治療はもちろんのこと、インプラント、矯正、ダイレクトボンディング、審美歯科など、幅広い専門的な治療を提供できるよう、常に研鑽を積んでおります。
患者様一人ひとりの口腔内の状態とニーズに合わせた最適な治療計画を立案し、長期的な視点での口腔健康をサポートできるよう、スタッフ一同、日々努力を重ねております。
お口に関して何かお困り事がございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に高崎ハルナモ歯科にご連絡ください。皆様のお口の健康を守るため、全力を尽くしてサポートさせていただきます。