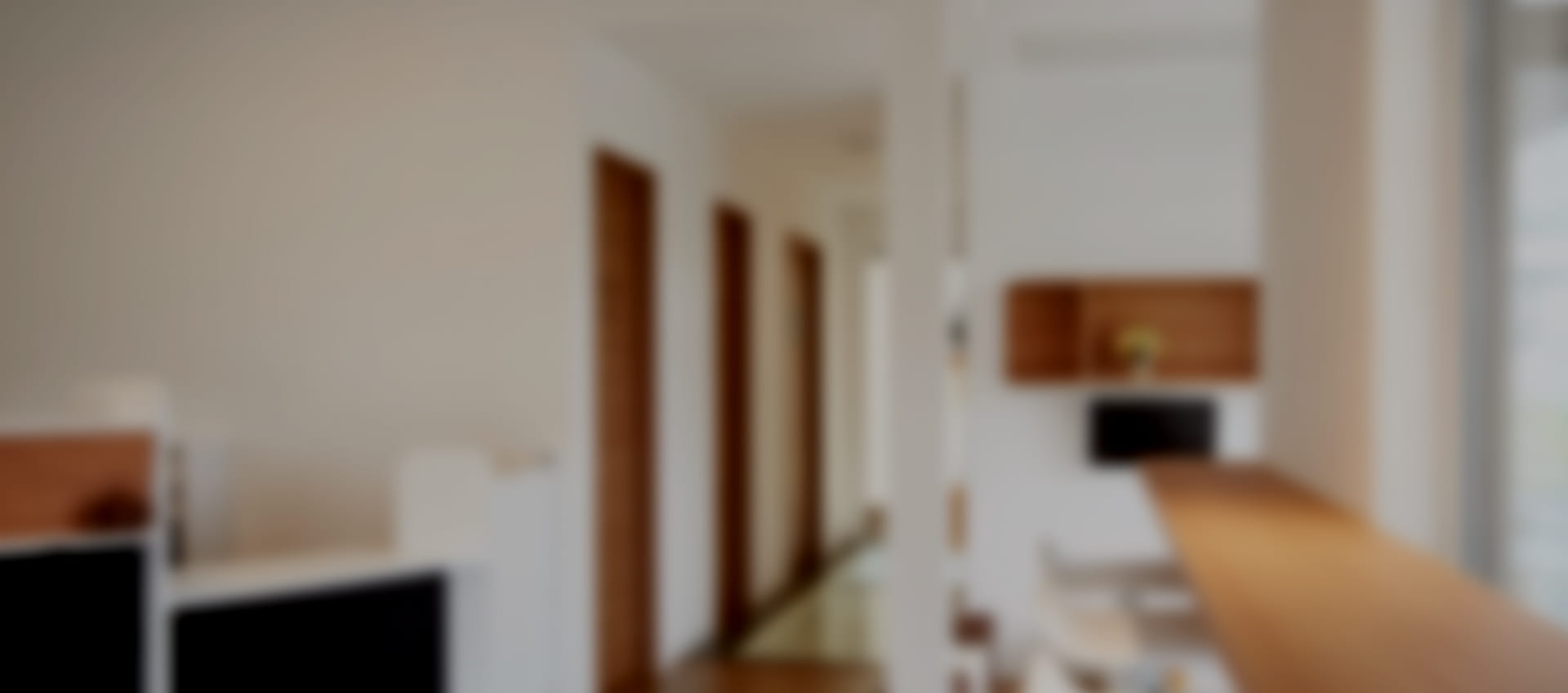JIADS ペリオコース第2回目に行ってきました。
いつもお世話になっております。
箕郷町コープ敷地内で開業している高崎ハルナモ歯科、院長の深澤です。
4月19日(土)、20日(日)は医院を休診とさせていただき、JIADS(The Japan Institute for Advanced Dental Studies)のペリオコース第2回目に参加してまいりました。JIADSの設立者の一人である小野善弘先生は、1982年にDr. Nevinsが主催する米国ボストンのIADSに留学されました。その後、故中村公雄先生と共に1988年にJIADSを設立されました。以来、数多くの歯科医師がJIADSで研鑽を積んでいます。
1日目は、貴和会新大阪診療所の佐々木猛先生から歯周治療におけるモチベーションについての講義から始まりました。貴和会は前述の小野先生と中村先生が開設された医療法人で、現在大阪に2箇所、東京に1箇所診療所があります。JIADSの特徴の一つにロンジェビティーがあります。ここで言うロンジェビティーとは、治療後トラブルなく30年経過した症例のことです。ロンジェビティーを達成するために、JIADSでは3つのコンセプトを掲げています。それは、cleansable periodontium(清掃性の高い歯周環境)、precise restoration(精密な補綴修復)、stable occlusion(安定した咬合)です。これらの要素が揃うことで、炎症と力のコントロールが可能になり、治療が長持ちします。炎症と力のコントロールを行うためには、私たち歯科医師の努力はもちろん不可欠ですが、患者さんが病気を理解し、治療に協力し、セルフケアを行うことも非常に重要です。佐々木先生は、患者さんに「この先生となら治療を一緒に頑張ろう」と思われるように、技術と知識を持ち合わせている「名医」であるだけでなく、人間的に惹きつける「良医」であることの必要性を強調されていました。
続いて、佐々木先生から歯周病の総論についての講義がありました。歯周病は骨の病気ですが、患者さんは歯周病を歯肉の病気と考えています。この認識のずれをいかに患者さんに理解してもらえるかが、治療を進める上で鍵となります。また患者さんは治療に対して、痛みがなく、治療費が安く、早く終わることを希望されますが、実際には痛みを伴い、費用もかかり、時間がかかることも理解してもらわなければなりません。歯周病は40歳以上の80%が罹患している慢性の生活習慣病で、中高年の歯の喪失原因第1位です。細菌感染によって歯周組織が破壊・喪失する病気ですが、自覚症状が少なく、ほとんど無症状のまま穏やかに進行していきます。一度壊れた歯周組織は治療を行っても完全に元に戻るわけではありません。そのため、歯周組織の破壊を食い止め、長期にわたり歯周組織の安定を図るためには、患者さんに治療の必要性を納得してもらい、協力をしてもらう重要性を強調されていました。
その後、貴和会理事の松井徳雄先生から、歯周治療の考え方についての講義に移りました。歯周治療は、初期治療、再評価、歯周外科、再評価、補綴処置、メインテナンスの順に治療が進んでいきます。各ステージで行うべき項目などを詳細に説明していただきました。またロンジェビティーを達成できる歯周組織の条件なども、臨床例などを通じて学ぶことができました。
次に酒井歯科クリニックの酒井和人先生によるMWFの講義と実習がありました。MWFはModified Widman Flapの略で、1974年に提唱された歯周外科手技の一つです。組織付着療法に分類される術式で、利点としては組織を温存でき、術前・術後の歯肉の位置が変化しにくいことが挙げられます。欠点としては歯周ポケットが再発しやすく、経年的に歯肉退縮しやすいことです。講義と実習ではMWFの切開線の決め方から縫合までのすべてのステップが細かく解説され、それぞれの段階での注意点やコツを一つ一つ確認しながら学ぶことができました。
2日目の20日は朝8時30分から講義が始まりました。おの歯科医院の小野晴彦先生からは、深い歯周ポケットに対する歯周外科・修復歯についての講義がありました。Apically Positioned Flapを略してAPFと言いますが、APFの考え方と臨床応用が講義の中心でした。APFは利点として、ポケット除去ができ、生物学的幅径の回復ができます。一方で技術的にはやや難しく、ポケット除去の結果、根面露出が大きくなり、知覚過敏、審美性、発音などの問題が起こる可能性もあります。そのため、歯冠修復予定歯に行う手技になります。
続けて小野先生から、歯周外科処置時に注意すべき生活習慣病についての講義がありました。高血圧、糖尿病、喫煙、抗血栓療法中の患者さんなどの注意事項を詳細に解説してくださいました。講義の中では、糖尿病専門医の西田亙先生の闘病記の話をされていて、医師の視点から「ペリオドンタルメディスン(歯周病が心臓病や糖尿病など全身の病気と深く関連していること)」について語られ、非常に興味深いものでした。
その後、酒井先生によるAPFについての講義と実習が行われました。APFは技術的に難しい部分もあるのですが、先生の丁寧な解説と実践的な実習のおかげで理解が深まりました。
高崎ハルナモ歯科では一般歯科のみならず、インプラント、矯正、ダイレクトボンディング、審美歯科などの専門的な治療を提供できるよう、常に研鑽を積んでおります。
何かお困り事がございましたら、お気軽にご連絡ください。